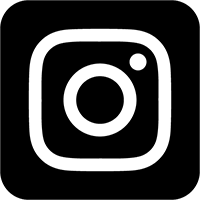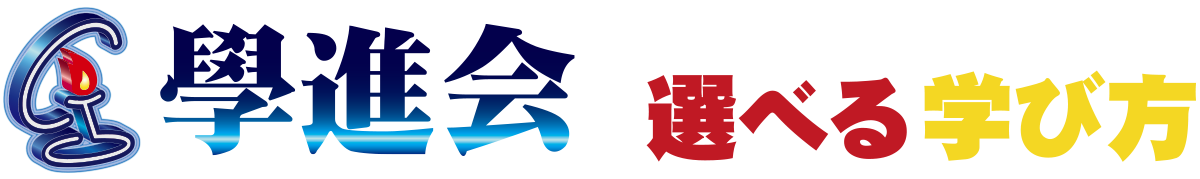受講:一斉授業・atama+・速読聴英語・河合塾マナビス
(この体験記の文章中のカラーリングは、本人がつけていたものを再現しました)
ⅰ.まえがき
「この状況で医学部は無理だよ。」
高校1年の夏に入塾の相談で来た僕は、塾頭にこう言われました。そして、この言葉を聞いた瞬間、僕の受験勉強が始まりました。部活も娯楽も捨て、全てを勉強に捧げた僕は、無理だと断言された医学部に現役で合格することができました。ここでは、そんな僕が実際にしていた勉強法や心構えを余すことなくお伝えします。これから僕が書くことは、凡人だった僕が国公立大学医学部に合格するまで実際にしていたことなので、才能の有無を問わず誰もが今すぐ実践できることばかりです。全ての効果は実証済なので、安心してマネして下さい。かなり長くなるので、気になる所だけでも目を通していただけると嬉しいです。
これを読んだ受験生のみなさんが、少しでも何かを掴んで飛躍してくれることを心から願っています。
もくじ
ⅰ.まえがき
ⅱ.自己紹介・遍歴
ⅲ.各教科ごとの勉強法 ⓪全体 ①国語 ②英語 ③数学 ④理科 ⑤面接、小論文、志望理由書
ⅳ.生活スタイル・マインド
Ⅴ.あとがき
ⅱ.自己紹介・遍歴
まずは簡単な自己紹介を。僕は福知山から少し離れたところにある宮津という地で生まれ育ちました。そして、特に何も考えず、宮津小、宮津中、そして宮津高校と順当に進学しました。ちなみに中学3年生までは野球とゲームに明け暮れていたので、勉強は一切していませんでした。
高校に入ったときは、学年全体で中の上くらいの学力だったと思います。この頃にただ「かっこいいから」という理由で医学部を目指すようになり、周りの友人や先生に宣言しました。そして自分の可能性だけを信じて勉強を始めました。何度もE判定を突きつけられ、時にはストレスで病気にかかり、時には塾頭にひどく叱られましたが、それでも毎日下剋上を夢見て、奇跡の大逆転を信じて勉強を続けました。
そうして度重なる困難をなんとか乗り越え、ついに受験本番を迎えました。推薦試験も共通テストも本番は全く緊張せず、むしろみなぎる闘志のせいで冬なのに汗をかいていました。こうして受験本番を最高のコンディションで戦うことができ、結果第一志望校に推薦で合格することができました。受かった瞬間は声が枯れるほど大声で叫びましたし、降っている雨がまるで祝福の紙吹雪のように感じました。また、学校の先生に受かった報告をしたときは、大半の先生に疑われたことを今でも覚えています。それほど誰もが僕の合格を予想していませんでした。
ⅲ.各教科ごとの勉強法
ここからは各教科の具体的な勉強法に伝、詳細に載せていきます.参考書については、塾内書店で売っているものを使えば、まず問題無いので、参考書で迷ったらすぐに塾の先生に相談しましょう.
⓪全体に共通すること
・質<<<量
勉強の質が少々悪くても量でカバーすることはできるが、その逆はほぼ無理→勉強量だけでも全国1位を目指そう
【理系科目&暗記事項】同じ問題集を3周以上解くのがマスト。1周目は間違えたところに印をつけていき、2周目は印のある箇所を解き直す。試験の前は、その印の多い箇所を拾っていくように復習。
【文系科目】異なる問題集を難易度順にたくさん取り組もう。同じ問題集の復習は1、2回ほどでOK。とにかく新しい文章に数多く触れて、少しでも多くの知識を詰め込む。
・常に疑問を持ち続ける
疑問が湧く=その分野を深く理解していると、思ってOK。どこがどう分からないかを明確に分析してから誰かに質問することで、より理解が深まる。受験前日まで、塾の先生や友人に嫌がられるくらい質問しよう。
・間違いながら覚える
僕らがしている勉強では、自分の間違いのせいで人に迷惑をかけたりすることは一切ない→間違いを恐れずむしろ楽しむくらいの感覚で勉強しよう!文系科目なら、間違えた問題や知らなかった知識をメモするノートを作るのがおすすめ。
・一点突破型よりもオールラウンダーの方が強い(国公立大志望者)
【私立大学志望者】自分の武器だけを徹底的に磨こう(苦手科目は赤点スレスレでOK)
【国公立大志望者】苦手な教科も捨てずに取り組もう(僕の友人にも理系科目は得意なのに文系科目が全くできないせいで共通テストに失敗し、志望校を変えた人がたくさんいました。また、僕は得意教科がなかったので、各科目の学年順位は低かったですが、総合順位は安定して上位をKeepすることができました。)
・苦手科目はちゃんと向き合えば得意科目(武器)になる可能性大
苦手科目=伸び代の塊。自分のさらなる飛躍のためと思って、楽しみながら取り組もう。
・雑学や常識を入れる
勉強において最も強い武器は知識!どんなに難解な文章や問題だとしても、その背景の知識が少しでもあれば、なんとか対応できる→特に文系科目で伸び悩んだら、新聞やテレビ(SNSはダメ)などで雑学や常識を頭に入れてみよう。
①国語
国語は学問の根幹→国語ができると他の科目も自然とできるようになる!文理関係なく大事!
・とにかくたくさん文章を読む
たくさんの文章に触れる。→知識をたくさん得られる。→次第にどの文章を読んでも「どこかで見たことがある、なんとなく知っている」と思うようになる。→問題文から素早く的確に情報を得ることができるようになる。→問題が解けるようになる。
・記述問題にたくさん触れる
国語の記述問題は苦手な人が多いが、国語はどれだけ記述問題を経験したかに左右される(僕は高1の春に死ぬほど国語の記述演習をしたおかげで、直近の模試で偏差値が24上がりました。)→国語を伸ばしたかったら記述問題を練習しよう(特に国語から逃げている国公立理系志望者)
はじめはなかなか書けないから、まずは時間を無視して自分なりにベストの答えを作る練習から始めよう。
・評論文:本文の大事そうな所に線を引く
まずは筆者の主張っぽいところに注目して線を引いてみよう(最初は難しいですが、慣れてくると自然と文章の大事そうなところが分かってきます。)⇒2周目を読むとき…その下線部を追うようにして読む。記述問題を解くとき…その下線部にあるワードを拾っていくイメージで書く。
・小説、古文、漢文:1周目…全体像の把握 2周目…設問に合わせた詳細な分析
まずは1周目で物語の全体像と人物関係を大まかに把握しよう(読書のように物語を楽しみながら素早く読めると◎)。2周目は設問の意図や解答に必要な要素を整理し、設問に直接関わる部分だけを読んで分析しよう。
・漢字、古典単語、文法、漢文句形は丸暗記
これらに関しては、何も考えずに丸暗記!(替え歌や語呂合わせで覚えるのがおすすめ)
②英語
英語は一番安定感があり、努力が反映されやすい↔すぐには伸びない→早い内に完成させよう!
・英単語、熟語、文法:多義語や派生も含めて丸暗記
語源、接頭辞、接尾辞から連想or語呂合わせで覚える(難関大志望者はマニアックなものも全て覚えよう)※単語を覚える=(発音+イメージ+つづり)を完璧に答えられる
英語の授業中に発音してみる(勇気のある人向け)→間違えても正解しても強烈に記憶に残る
・長文:評論…3つのポイントを押さえる。 小説…とにかく時系列を整理する
評論系の文章:言い換え表現、逆説、強調(構文)の3つを意識+文章全体の流れと筆者の主張を掴む
小説系の文章:時系列が分かる単語(today、~ago、2020sなど)に印をつける。段落や場面が切り替わるごとに頭を整理する時間をとるなどして、出来事の順序を正確に追う。
・英作:問題文を易しい日本語に言い換え+テンプレートをストック
問題文の日本語をいかに言い換えるか(理系っぽく言えば、いかに同値変形をうまくできるか)がカギ。→これさえできれば、高1までの英単語と文法でなんとかなる。知っていないと書けない構文や文字数を稼ぎやすい構文は、最低限ストックしておこう。
・構文読解:クイズ感覚で楽しみながら解く
謎解きやクイズ感覚で楽しく演習するのがコツ!作問者の意図や隠れている構文を見抜いたときの快感を糧にして、たくさん練習しよう(難関大志望者は強調構文や倒置表現などのマニアックな表現技法も識別できるようにしよう)
・リスニング:毎日なにかしら聞くのみ
リスニング対策は、聴いて慣らす以外にない!毎日5分だけでもいいから、音声を聞いたり音声に合わせて音読したりしよう。※僕の経験上、洋楽、映画、YouTubeで耳慣らしをするのは、受験生には難しすぎるので、絶対にやめましょう。読んだり聴いたりした英文を頭の中で即座にイメージに落とし込む訓練をしよう。→最初はかなり難しく感じるが、数をこなすと音声や読むスピードに頭がついてくるようになる。→英語の処理速度が急上昇!
③数学
一番ブレが大きく、調子に左右される→ライバルと差を付けるチャンスあり
・常に計算ミスを確認する
1 自分の書いた解答を遠目から客観視する視点を持つ(もう一人の自分を持つイメージ)
2 別の解法で検算する
3 逆から解いても成り立つか調べる
※医学部を目指す人に知っておいて欲しいこととして、地方国公立の医学部の試験では、難しい問題よりもミスしやすい問題がたくさん出てきます。そして例えば、工学部では-5点ほどのミスを医学部では-20点にするという方式で受験生をふるいにかけています。つまり、1つの計算ミスであっさり落とされてしまうということです。なので、医学部を目指す人は、難しい問題ではなく標準レベルの問題をミス無く完璧に解く練習をして下さい。
・問題を分析する
いきなり解答を書き始めるのではなく、まずは問題文で与えられた条件を整理したり問題構成や流れを把握したりして、出題者の意図を考えるようにしよう(特に難関大は大問1や(1)を難しくしている大学も多く、そこでいかに意図をくみ取って正確に答えられるかどうかで、大きく差がつきます。)
・モヤモヤしながら解く
数学の問題を解いていて、途中で手が止まったり、解答解説を見て「そんな解法思いつかない」と思ったりして、モヤモヤ(僕の場合はイライラ)したら、そのモヤモヤに耐えながら解消できるまで手を動かし続けよう(特に難しい問題になると発想がモノをいうようになるので、最初の一行すら書けないこともあります。その時すぐに解答解説を見て受け入れるのではなく、その発想の出所や根拠、そして自分の考えとの相違点や類似点まで細かく分析して、モヤモヤを完全に解消しましょう)
・高2までは難しい問題を時間をかけて解ききる経験を積む
難関大になると、1問に20分~30分以上かかることがザラにある。→途中で集中力や思考力が落ちないように、日頃から時間をかけて解ききる経験をたくさん積もう。※高3からは理科や社会も忙しくなるので、1問に30分以上かけないようにしよう。
④理科
僕の大の苦手科目なので、よいアドバイスができません。ごめんなさい。
・履修する時期が遅く、完成しないことの方が多い↔本番前日まで伸び続ける
最後まで根気よく勉強を続けよう(僕も前日に勉強したところが次の日の試験に出ることは、よくありました)
・定期テストごとにその範囲、単元を完璧に仕上げる
他の科目に遅れを取ることが多く、じっくり演習する暇がない。→理科だけは定期テストで満点をとるくらい本気で勉強しよう。
【物理】
・公式は導き出し方から覚える
覚える公式がやたらと多いため、他の公式と混同することがよくある。→最低限覚える公式だけを覚えておいて、後は自力で導出する訓練をしよう(最初は面倒ですが、だんだん導出しなくても勝手に覚えていくので大丈夫です)
【化学】
・とにかく暗記しまくる
化学は無機有機の分野になった瞬間、ただの暗記科目に変貌する。→膨大な量の知識を一気に覚えることが要求されるため、英単語などと同様に無理矢理頭に叩き込もう(語呂合わせでまとめて覚えるのが一番おすすめ)
⑤面接、小論文、志望理由書
一般的な科目と違って、専門知識や非認知能力が必要。→日頃からアンテナを張って、情報を掴みにいく+自分という人間に向き合う。
・面接、小論文、志望理由書は最初みんなできない→失敗を恐れず、とにかく回数をこなして慣れる
面接、小論文、志望理由書は誰もが初心者。→最初のうちは恥ずかしいくらい全くできない(僕も最初の頃は、心が折れそうになるくらいみっちり指導を受けました)得意不得意はあるにしても、練習すれば誰でも必ず上手くなる!→諦めず回数をこなして少しずつ慣れていこう。
・日頃からイベントにたくさん参加する
特に医療系や教育系は、自分の目で見て肌で実感するのが最も効果的な勉強になる。見学会や実習などのイベントで触れた現場の生の声や体験談を面接や志望理由書で使うと、説得力が増してよりいいものに仕上がる。→将来の進路に迷っている人も、とにかくイベントに参加してみよう。
【面接・志望理由書】
・自分と対話し、自分の事を深く知る
面接や志望理由書で他人と差をつけるために必要なこと
1 自分のこと(長所短所、性格、経験など)を誰よりも理解すること
2 志望動機を明確にすること
面接や志望理由書は、自分を「売り込む」チャンス。→恥ずかしがらず、堂々と伝えよう。素直な気持ちを伝えることができれば、必ず大学側に想いが届く!
・慣れてきたら先生や親など、相手を変えてみる
面接になれてきたら、怖い先生や偉い先生に面接をしてもらい、本番さながらの緊張感を体感してみよう。志望理由書も完成したら色々な人に見てもらって、第三者の意見をたくさん聞こう。
【小論文】
・国語の勉強を通して文章を書くことへの抵抗を減らす
小論文は100~800字記述の問題が当たり前。→国語の問題を通して、長い文を構成して表現する力を養おう。
・テンプレートに当てはめない
採点者はその分野のプロフェッショナル→ワンパターンな文章や浅はかな考えは、すぐ見抜かれる。
ダメなテンプレートの例
(1)1段落目に本文の要約、2段落目に「だがしかし、~」→筆者の意見を真っ向から否定する
(2)ただ筆者の意見に賛同するだけ
ⅳ. 生活スタイル・マインド
次は僕が実際にやっていた生活スタイルやマインドを全てお伝えします。
【生活スタイル】
・勉強モードへの切り替えを素早く
多くの人はこの切り替えが遅く、限りある時間を浪費してしまいがち。→いつでも勉強モードに入れるように常日頃から勉強のことを考えよう※ただし、学校祭や修学旅行といった学校行事は勉強を忘れて、全力で楽しんでもいいと思います。僕も修学旅行では実行委員を、学校祭では競技リーダーを務めていました。僕らは受験生であると同時に高校生でもあるので、学校行事くらいは思いっきり楽しんでしまいましょう。
・隙間時間(休み時間、登下校中、待ち時間)を勉強で埋める
残念ながら、都会の中高一貫校や超有名進学校の生徒は、僕らよりも段違いに地頭が良く、履修するスピードや受験勉強を開始するタイミングが圧倒的に早い。→難関大を目指す人は、そういう敵+浪人生と競わなければならないと自覚しておこう。自分より強い敵と同等に戦うには、「時間」を上手く使うしかない!→強敵との差を無くすために、隙間時間を時間で埋めよう(最初は英単語に目を通すだけでも全然OKです。ちなみに僕は、下敷きと要らない紙を常に持っておいて、どこでも数学の問題を解けるようにしていました。)
・勉強時間は土日13時間以上、平日6時間以上、受験期は1日15時間(←僕が実際にしていた勉強時間)
周りと差をつけるために、まずは勉強時間から増やそう(僕はご飯中やお風呂の中でも勉強していました。)※ただし、睡眠時間は必ず6時間以上確保しましょう。寝不足と体調不良は勉強の効率を大きく下げます。
・現状を打破したいなら環境を変える
賢い人達と関わる→自分が賢くないことに気付く→自分も賢くなりたいと強く思うようになる→賢い人から多くのことを学ぼうとする→自分も賢くなる。このサイクルによって、人は賢くなれます。(僕は高校1年の夏に本気で自分を変えたいと思ったので、この塾に入りました。はじめは授業のスピードやレベルに圧倒され、ついていくのに精一杯でしたが、頑張って通い続けていると…気付けば授業中に発言出来るようになっていました。)
【マインド】
・どんな時も明るく・元気に!(いちばん大事)
どんなに失敗しても、とにかく前を向きましょう。どれだけ状況が絶望的であっても、それを笑い飛ばして楽しんでやりましょう。そうすれば必ず結果が出ます。僕は高校入学当初から、本試験前日まで国公立医学部レベルの学力に達したことはなかったですが、それでも毎日前向きに勉強していたからこそ合格できたのだと思っています。
状況を前向きに捉える例
「テストの点が悪かった」→「自分にはまだ伸びしろがあって、これからが楽しみだ!」
「模試で失敗した」→「本番じゃなくてラッキー」
「ライバル達に遅れをとっている」→「どうせ合格するなら、下剋上の方がカッコイイ!」
・二兎追うもの一兎を得ず
僕は2年生の夏に部活をやめました。僕は今までスポーツを軸に生きてきたので、部活をやめることは生きがいを捨てることと同義でした。それでもこうして合格体験記を書くことができている今、あの時部活をやめてよかったと思っています。みなさんに部活をやめろとは決して言いません。なぜなら、部活をやめても学力が伸びる保証はないからです。ですが、部活と勉強の二兎を追うなら一兎も得られない可能性があることも考えておいて下さい。
・プライド
僕の勉強の原動力は、ここにありました。僕は小学生から受験をして、私立の進学校や中高一貫校に通うようなエリート達には絶対負けたくないと、昔から思っていました。なぜなら、生れ持った才能や親の経済力で人生が決まるという現実がイヤだったからです。そんな貧乏くさい考えでも、僕を突き動かすには十分な動機になりました。
みなさんの中にも、何か譲れないものが必ずあるはずです。それがライバルに勝つことでも、大学名や学部にこだわることでも構いません。一生で一度の受験期ですから、心の中にあるそのプライドを大切にして下さい。
・未来の輝かしい自分を思い描く
夢や目標を叶えた瞬間を鮮明に想像する→心からワクワクしてくる→脳が自身の現状と、その夢を叶えるにはどうすればいいかを勝手に分析し始める→勉強しなければならないという結論に至る→自然と勉強したくなる。(夢や目標は、モテたいとかお金持ちになりたいといった、純粋な欲望であればあるほど良いと思います。)
・諦めない
僕が合格できた最大の理由は、ここにあります。僕に何か才能があるとすれば、それは諦めない力だと思います。僕はどれだけ絶望的であっても、決して第一志望を変えませんでした。なぜなら、自分は最後の最後に大逆転を起こすと信じていたからです。もちろん根拠はありません。ですが、その大逆転が起こる可能性が0%でない限り、信じる価値は大いにあると思います。ですから、みなさんも最後まで第一志望を変えないで下さい。特に国公立志望者は、共通テストが終わるまでは諦めないで下さい。スポーツと同じように、受験本番も何が起こるか分かりません。受験に成功するのは、頭のいい人でも才能のある人でもありません。最後まで諦めない人です。
ⅴ.あとがき
はじめに、塾の先生方へ。約2年半の間、本当にお世話になりました。未知の環境に一人で飛び込んだため、いつも孤独と不安でいっぱいでしたが、先生方の温かいご指導のおかげで、最後まで辞めずに走りきることができました。この塾で得た経験は、一生の宝物です。僕に「ホンモノの勉強」を教えていただき、本当にありがとうございました。
最後に、受験生のみなさんへ。何度も言うとおり僕には勉学に関する才能も素質も全くありませんでしたが、こんな僕でも国公立医学部に現役で合格することができました。だから皆さんなら絶対に大丈夫です。
僕からしてみれば、この塾の近くに住んで、学力水準の高い福知山の高校に通っている皆さんが、とても羨ましいです(笑)。皆さんは、環境も才能も確実に恵まれている側ですから、自信を持って勉強に励んで下さい。そして、僕を追い越していって下さい。皆さんの合格通知と進路実績を楽しみにしています。