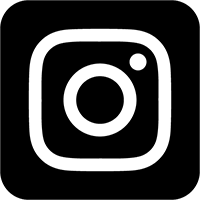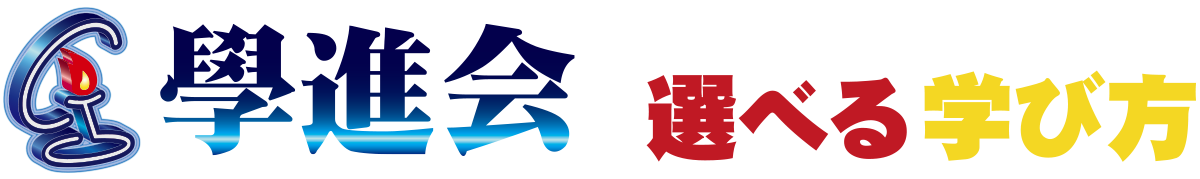受講:一斉授業
その他合格校:東京理科大学(薬)・同志社大学・立命館大学(薬)・兵庫医科大学(補欠合格)
大学で1年過ごした後、提出してくれた合格体験記です。
【目次】
1.自己紹介
2.勉強や受験について
3.メンタルの保ち方
4.医学部を目指す人へ
5.医学部の大学生活について
6.お世話になった先生方へ
【1.自己紹介】
こんにちは。島根大学の医学部に入学して、早1年が経ちました。受験に関することはもちろん、大学生活の話も書こうと思うので、よかったら参考にしてみて下さい。この合格体験記が少しでも皆さんの役に立てれば嬉しいです。
私は高校2年生になる前の3月から2年弱、學進会に通っていました。高校に入学したあと、周りに医療系の学部を目指していた人が多かったことに影響され、高1の夏から漠然と医学部を目指すようになりました。そして塾に通うことを検討し、同じ学校の医学部を目指す友達が複数人通っていた學進会のことを知りました。
入塾する前、塾頭に模試を見ていただきながら面談しました。そこで私の学力状況を的確に指摘され(中学まではセンスでなんとなく解けてきてしまったが、高校に入って通用しなくなったのでは?基礎はできているけど応用部分になると手が出せなくなるのでは?などといった内容だったと思います)それがあまりにもその通りだったので、この先生についていこうと入塾を決めました。
學進会は他の塾より厳しいとよく言われますよね。確かに先生方は時には厳しいし、周りの塾生のレベルが高くて付いていくのに必死だし…という環境ですが、ある程度プレッシャーがかかっていたおかげで最後まで努力できたと思っています。高みを目指し、努力し続けたい人にはとっても良い環境だと思います。
私は他の塾生に比べ入塾が遅かったこともあり、当初はアウェー感を感じていましたが、熱心で塾生一人一人をしっかり見て下さっている先生方に囲まれ、周りの塾生の知識量や勉強量に刺激され、なんとか医学部に合格することができました。私があの時入塾を決意していなかったら、医学部に合格するなんて到底できなかったと思います。私は推薦入試で合格しており、最後まで学力的には一般入試での合格は難しい状況でしたが、それでも合格できたのは、學進会の存在がとても大きいです。
【2.勉強や受験について】
先輩方の合格体験記には、使っていた参考書や、オススメの勉強法などの役に立つ情報がたくさん書かれていることと思います。しかし私は、勉強の効率がよくなく、実際学力も十分には足りておらず、今思い返しても受験生の時の勉強法が最善だったとは全く思わないので、勉強については他の合格体験記を読むことをお勧めします。一応私の勉強スタイルについて記しておきます。
参考書や問題集は、ほとんど学校で配布されたものか塾のテキストのみを使っていました。色々手を出してもやりきれないと思っていたのと、自分のレベル・志望校を考慮すると、基礎固め中心にした方が適切だと考えたためです。基礎をないがしろにして応用を解くことはできません。ただ難しい問題の解法を覚えるのではなく、なぜそうなるのかを理解するためにも、基礎をしっかり理解することは必要だと思います。
以下、使用した参考書、問題集のうち、積極的に取り組んだ&自分に合っていたものを紹介します。
◎数学
・4STEP ⅠA、ⅡB、Ⅲ(学校配布)
私はチャートより4STEP派で、チャートはほとんど使いませんでした。4STEPの別冊解答である程度理解できる人は、小さくて軽いし、これで良いのでは?と思います。皆さん結構4STEPバカにしていますが、基礎を身につけるという面ではちょうどいいと思います。多くはないですが、発展問題や入試問題も掲載されているため、数学の基礎を中心に問題をこなしたい人は、しっかり取り組んでもよいのではないでしょうか。
私は全部やらないと気が済まない性格なので、A問題B問題ともに1から順に全て解き、定期テスト前には*付きの問題を再度解くようにしていました(これはしなくていいと思う)。解説を読んでも分からないところは、学校の先生に聞きに行っていました。
・スタンダード数学演習ⅠⅡAB(学校配布)
高3から、学校の演習授業で使っていました。入試問題やその改問題が掲載されており、解けなさすぎて泣かされました。それまでの「ある程度数学できるようになってきたかも!」という自信が粉々に崩れました。けれども、発展的な入試問題やその解法に触れることができるため、基礎をしっかり身につけた上で取り組むと力がつくと思います。
・クリアー数学演習Ⅲ(学校配布)
これも高3から、学校の演習授業で使っていました。各項目で難易度順に問題が掲載されているため、易しい問題から順に解いていくとよいです。スタ演と同様、基礎を身につけてから取り組むと良いと思います。
◎化学
・セミナー化学(学校配布)
1年生から化学基礎、化学で使いました。化学が大の苦手だったため、まず教科書やセミナーのまとめのページで復習し、基本問題、発展問題と順に解いていきました。
・化学基礎問題精講(学校配布)
化学があまりにも分からなかったため、高2の春休みから高3の春にかけて、一度基礎からやり直そうと思って使いました。自分がそもそも何が分かっていないかを把握するのによかったです。
・化学重要問題集(学校配布)
重要問題集でザッと問題に取り組み、あまりできなかった単元は教科書を見直したり、セミナーの問題を解き直したりして使いました。
◎物理
・実践アクセス総合物理(学校配布)
1年生から物理基礎、物理で使いました。高3の春には物理基礎から順に基本問題のみ解き直していき、余裕があれば発展問題にも取り組むというように使い、理解できるようになりました。
・物理重要問題集(学校配布)
アクセスのやり直しをした後に使いました。
◎英語
・システム英単語(学校配布)
できれば1年生のうちに一度最後までやりきって下さい。英単語はとにかく何周もして頭に入れるのがいいと思います。私はQuizletという英単語アプリでシス単を何周もしていました。
・速読英単語 上級編
シス単をある程度覚えた後、読解力を鍛えたかったので、電車の中で読み物として読んでいました。
・Next Stage(学校配布)
文法や語法、イディオムが身に付きます。学校で小テストがあったため、頻繁に使っていたと思います。まず問題を解き、答え合せを兼ねて解説をザッと読んでいく、という使い方をしていました。
・ジーニアス英熟語(塾配布)
・英文解釈の技術
・塾のプリント
英文読解は、塾の授業で使うプリントにお世話になりました。
◎共通テスト対策
・河合塾 Jシリーズ(全科目)…共テ形式の問題集
・駿台 実践問題集(化学・物理)…共テ予想問題集
・Z会 共通テスト実践模試(化学・物理)…共テ予想問題集
・時代と流れで覚える!世界史B用語…教科書より若干情報が少ないですが、地図や図解が豊富で、流れが分かり易いです。
・完成古文単語321(古文、学校配布)
・体系古典文法九訂版(古文、学校配布)…古典文法はずっとこれを使っていました。
・新明説漢文(漢文、学校配布)…漢文の句法、語彙など。
ここから、私の高校3年生のときの勉強スタイルについて少し書こうと思います。夏から共通テストまでは、学校や塾の授業でそれぞれの科目の演習・二次対策をし、自分では共テ対策に比重を置いて勉強していました。共テ対策はとにかく共テ形式の問題を解いていくことが一番だと思います。現代文と古典漢文は、学校の授業が共テ形式の問題を解くものだったため、授業に真剣に取り組むことで勉強時間を確保していました。化学と物理は特に苦手だったため、学校経由で購入した河合塾Jシリーズに加え、共テ予想問題集を2社分購入して取り組みました。共テ形式の問題に取り組むときは、必ず本番通り時間を計ってやって下さい。時間内にどこまで解けるのか?あと何分あれば残りが解けるのか?を把握するのが重要です。
共栄の人は、高3で7時間目が無くなり、自由選択の7校時補講が開校されると思いますが、私は数学の講座2つ(共テ対策、二次対策)と、化学、物理をとっていました。夏休みの希望者講習では、共テ数学補習、数Ⅲ補習、共テ英語補習、英語二次対策補習、共テ化学補習、マーク世界史補習をとっていました。塾などで忙しいと思いますが、普段よりも少ない人数で、先生にも質問しやすくなるため、共栄生は余裕があるなら参加してみて下さい。
また共栄では、共テ直前の12月下旬~1月上旬に共通テストパックを演習すると思いますが、それも学校で受けられる分は、ぜひ参加すると良いと思います。共テ対策は数をこなしていくのが効果的だと思うので、そのような機会を積極的に活用してみて下さい。
次に勉強の場所についてです。お気に入りの勉強場所を見つけることをおすすめします。私にとってのお気に入りの場所は、学校の教室でした。放課後になるとすぐに塾に向かうクラスメイトが多く、人がほとんどいなくなるため、大人数の空間が苦手な私は、とても集中して勉強することができました。分からないことがあればすぐに先生に聞けるのもメリットでした。
また、高3になってからは、朝授業が始まる1時間前に登校し、空き教室を使って勉強するのを日課にしていました。塾の自習室や学校、図書館など、自分に合った空間を探してみて下さい。もし勉強途中で集中力が切れてしまったときは、勉強場所を変えたり、思い切って短時間寝てみたりするのがおすすめです。
【3.メンタルの保ち方】
高校3年生になると、特に受験期には精神的に不安定になったり、落ち込みやすくなったりする人が少なくありません。私は自他共に認める、メンタル激弱人間だったため、そんな私なりの対処法を紹介します。
①楽しみなことを作る
小さなことでいいので、楽しみなこと、楽しみな日をときおり設定して下さい。例えば、ご褒美スイーツ、友達とのご飯、好きなアーティストの新曲公開日…などが良いかもしれません。私は「受験生だから遠出するな」とは全く思いません。ずっと勉強ばかりだとシンドイので、たまには遊びにいってリフレッシュすることも重要だと思います。大事なのは、その楽しみをモチベーションにして、その日まで勉強を頑張ろうとすることです。私自身、高3になった当初は学校行事だけを楽しみに日々の勉強を頑張っていたのですが、校外学習や文化祭などの行事が終わるたびに「あと楽しみが○○しか残っていない、その後は受験でシンドイだけだ…」と考えてしまい、ネガティブな気持ちになっていました。クラス全体も行事が終わった後は、なんとなく無気力な雰囲気になっていたのを覚えています。このように年に数回ある大きな出来事だけを楽しみにしてしまうと、それが終わった途端にモチベーションがなくなってしまう可能性があるので、できればもっと頻繁に、大きすぎない楽しみを設定するといいと思います。
私は楽しい学校行事が全て終わってしまってからは、週末に食べるスイーツや、たまに弾くピアノ、近場へのお出かけなどを楽しみに、それを楽しむために今は勉強頑張るぞ!というように考えていました。
②人と関わる
これはひと学年上の先輩や学校の先生から言われたことです。先生からは、もし精神的にしんどくなって授業に出たくなくなっても、顔だけを見せに来いと言われていました。先輩からも同じようなことを言われたと記憶しています。孤独な状態でいると、一人で悩みを抱え込んでしまい、負のスパイラルから抜け出せなくなるそうです。
共栄の高3は、3学期には授業がないため、学校に行かずに一人で勉強する人も多いと思いますが、私は受験が終わるまで毎日学校に通っていました。友達や先生と喋るのは、昼食時や帰る前のほんの少しだけでしたが、それだけでも気持ちが軽くなったため、一人でいるよりよかったと思っています。話を聞いた先輩は、LINEグループを作って、励ましあっていたそうです。
とはいえ、受験期はみんなストレスを感じていて、以前よりイライラしやすくなったり、些細なことが気になったり…と、性格が変化して、友達とギクシャクしてしまうこともあるかもしれません。その時は友達に気を使わず距離をおいてしまってもよいので、自分を最優先して下さい。受験が終わって、お互い新生活が始まって心に余裕ができると、自然とよい距離感になっていたりしますよ。
③相談できる人を見つける
②と似たような内容ですが、悩んでいることがあれば、一人で抱え込まず、誰かに相談してみるのがよいと思います。可能ならば複数人に話を聞いてもらうと、それぞれの意見やアドバイスが聞けて、納得する答えが見つかるかもしれません。
私は学校の担任の先生によく話を聞いてもらっていました。1回に2時間近く相談するし、3年生になってからは、辛くてよく泣くし…で、迷惑だったと思いますが、思いを話すことで自分がどうしたいのかに気付くことができ、気持ちを切り替えることができました。
勉強について悩んでいたときは、学校の各教科の先生や塾の先生に相談して、それぞれの科目への取り組み方を見直していました。もし身近に相談しやすい人がいなければ、今の時代、AIに話を聞いてもらうこともできるので、とにかく一人で悩まないで下さい!
④志望校へのモチベーションを高める
受験勉強がイヤになったときは、志望校のことを調べて「受験を乗り越えたら、楽しい大学生活が待っている!」と、考えて下さい。いまどき各大学や、部活・サークルのSNSアカウントがあるので、それらを見てみるとモチベーションが上がるかもしれません。今は辛いと思いますが、あと少し頑張れば、楽しいキャンパスライフが待っていますよ!
⑤模試の判定システムを活用する
模試では志望校の欄にほぼ医学部のみを書いていて、学力が十分でなかったために模試判定は毎回C~E…ごくたまに調子が良くてBになるといった感じでした。しかし、周りの友達が安定してA判定やB判定をもらっていたため、自分の判定に毎回ショックを受けていました。
そこで少し情けないのですが、次のような方法でメンタルを保っていました。河合塾のサイトに模試判定システムというのがあり、自分の全統模試の成績を入力することで志望欄に書ききれなかった大学の判定が手軽に分かります。ここに医学部以外の様々な学部や様々な大学の判定を行い、「ここならA判定なんだ!」と知ることで、自信に繋げていました。医学部を目指しているから判定が振るわないけれど、それ以外に目を向けてみると、自分の学力はここまで通用するんだ!というのを実感するためにやっていました。
もちろんこのシステムは、志望校欄に書ききれなかった場合にも利用できるので、ぜひ活用することをおすすめします。私は全国の医学部の判定を出して、どこが自分に合っているのかの参考にしたり、私立大学の理系学部の判定を出して、併願校を決める際の参考にしたりしていました。
⑥試験当日に強いメンタルを持っていく
最後は思い込みです。私の失敗例と、そこから学んだ対処法を説明します。
私は、共通テスト1日目はメンタル面で何の対策もせずに臨んでしまいました。共栄生は少ないため、自分の周りに友達はいませんでしたが、他校の生徒は数人ずつ固まって座っていました。そんな中、休憩時間になると他校の生徒達が「予想より簡単やったな!」「自己採点の結果が良かったら○○大に出願できそう!」「体感○割くらいとれたかも!」と話し始めます。そのような状況の中に一人でいる私は、メンタルをどんどん削られ、1日目のラストの英語で失敗してしまったこともあり、電車の中で号泣したのを覚えています。その話を2日目の朝に高校の先生にすると、いくつかアドバイスをくれました。試験の出来が良かったことを大声で話すのは、それを聞いている人にプレッシャーを与えるためにわざとやっているのだから、気にしたら思うつぼであること。試験会場では、自分が一番賢いと信じて、自分に解けなかった問題は他の人も解けていないと思うこと。これが本当かどうかはさておき、このように思い込むことで、試験会場の独特の空気にも耐えられたと思っています。それからは、試験会場には必ずイヤホンを持参し、休憩時間にはイヤホンをつけて周りの声を聞かないようにしていました。誰かが試験について話しているのを耳にしても、「わざと聞こえるようにアピールしとるんかな?そんなことをしない私の方が人間としては大人やな」と、謎理論で聞き流していました。そして試験が思うように解けなくても、「私が解けなかったということは、メッチャ難しい問題やったんや!この問題で差はつかないはず!」と思い込み、落ち込まないようにしていました。
むりやりにでもいいので、当日はメンタルがとても強い人間になったと思い込んで、できる限りポジティブな考えで試験に臨んでください。
【4.医学部を目指す人へ】
医学部受験は特殊で、大学ごとの出題傾向に大きく差があったり、全員に面接が実施されたりします。そのため、自分が受ける大学について、早くからしっかりと理解することが必要です。
私は推薦で合格していますが、医学部を考えている人は、ぜひ推薦入試も視野に入れてほしいです。推薦入試を受けるとなると、3年間の評定や小論文が必要になることがありますが、評定をとるために真面目に勉強することは、そのまま自分の学力に繋がりますし、小論文を書く力は私立大医学部入試でも使えます。なにより、ただでさえ難関の医学部に入学するチャンスを増やせます。また、面接や小論文の配点が高かったり、個別学力試験が無かったり、一般入試と比べると学力のハードルが低いことが多いので、低学年のうちから推薦入試についても知っておくと良いかもしれません。
推薦入試でどの大学に出願するかを決めるとき、島根大学を含めて3校検討しました。入試科目や共通テストの配点、面接や小論文の配点を考えた結果、島根大学に出願しました。私はもともと作文が得意で、面接もそこまで苦手でなかったことから、小論文があり、個別試験(面接・小論文)の配点が他より高い島根大学を選びました。また、前期試験も受けるつもりでいたため、共通テストリサーチの結果をもとに、共テや二次試験の各科目配点の他、二次試験の傾向などを考えて、前期は島根とは別の大学に出願しました。
医学部を目指す人で、どの大学に出願するかは、とても悩むところだと思います。私は大学名より医学部に入ることが最優先だったため、当初は医学部に入れるなら日本中のどこでも構わないと考えていました。しかし、いざ出願するときになって、同じ偏差値帯の大学を比べたときに「いくら可能性が高くても、地元県から遠すぎるのは嫌だ」と思うようになり、各大学の問題傾向も把握した上で、中国四国内に絞りました。
私は共テが終わってから出願校についてものすごく悩んだので、医学部を目指している人はぜひ早めから志望校何校かの問題の傾向(基礎力重視、応用力重視など)や配点、立地などをよく調べておくことをおすすめします。
医学部の面接についてですが、医学部入試は学力が高くても、面接の点数が著しく低ければ落とされると聞いたことがあると思います。そこからも分かるように、面接は重要です。私は、学校の進路学習で面接に向けての時間が複数回あったため、まずはそこでよく聞かれる質問に対して答えられるように練習しました。推薦入試の個別試験が近くなってからは、学校の先生に個別で面接の練習をしてもらい、質問に対する答えをあらためて熟考して修正し、面接時の表情や話し方も含めて対策してもらいました。
また、医学部面接用の参考書を1冊買い、親にそこに掲載されている質問をランダムにしてもらい、答えるという練習をしていました。直前期には予備校のwebページなどで過去に実際に聞かれた質問を把握し、自分なりの答えを考えました。
このようにしっかりと準備して面接に臨んだおかげか、緊張していたものの焦ること無く受け答えでき、面接は9割得点していました。面接は対策すればその分結果に反映されるので、あまり軽視せずに準備して下さい。
【5.医学部の大学生活について】
医学部生活6年の内たった1年しか経験していませんが、大学生活について少しだけ書きたいと思います。
受験生のときは医学部に合格することがゴールのように感じていましたが、大学入学はスタートであり、これからいくつもの難関が待ち受けています。まず大きな難関を挙げると、4年生のCBT 、OSCE、そして6年生の医師国家試験です。
4年生では、CBTという医学知識の理解を評価する学力試験と、OSCEという医療面接や手技などの実技試験があり、この2つに合格しないと、その後の臨床実習に参加出来ません。また、6年生の2月には医師国家試験があり、これらの試験に合格するために膨大な勉強量が必要になります。
それ以外でも、医学部の授業は必修ばかりなので、1つでも単位を落とすと留年してしまいます。学年が上がるに連れて講義の内容が難しくなり、試験の頻度も増えていくため、気を抜くことはできません。私は高校時代からずっと理科が苦手なのですが、医学部の特性上、化学や生物系の科目が多く、なかなか苦戦しています。これからさらに忙しく難しくなっていくのかと思うと、こんな自分が6年間で医師になれるのだろうか?と、不安になることもあります。
このように大変な面もありますが、メリハリをつけることで、それなりに充実した学生生活を送ることも可能です。多くの学生が何らかの部活に所属しており、中にはいくつもの部活を兼部している人もいます。勉強と部活、バイトを両立させている人もたくさんいます。
そして医学部には現役生だけでなく、浪人生や再受験生、編入生が多く在籍しており、さらに6学年あるため、幅広い年齢で多種多様な経歴を持つ人達と仲よくなれます。この特徴は医学部ならではの長所ではないかと思います。
キャンパスが地方なので、都会の大学生のような楽しみ方はできないし、毎日の授業は忙しくて大変ですが、今の環境を自分なりに楽しみたいと思っています。
【6.お世話になった先生方へ】
○塾頭
数学の授業はほとんど塾頭の授業を受けていて、進路指導の面でもとてもお世話になりました。高3になってもなかなか学力が伸びず、実は模試を見せに行くときに毎回「今度こそ、諦めろって言われるかも…」と思いながら見せていました。ですが塾頭は、そんな私に諦めろとは言わず、いつも的確なアドバイスをくださり、最後にはいつも「頑張れ!」と、声をかけて下さったのを覚えています。その言葉を聞いて、「まだ諦めなくていいんだ」と、努力することができました。
面談のたびに受験や大学に関する様々な情報を教えていただき、大学を選ぶ際にとても参考になりました。推薦入試で、どこに出願するかを迷っているときも塾頭に相談して、そのまま島根大学に出願することに決めました。私を医学部に合格させていただき、本当にありがとうございました。
○奧さん
自習空間を出るときの「いってらっしゃい!」という言葉にとても励まされました。一度授業中に急な腹痛と吐き気でしんどくなったことがあり、電車の時間まで受付の奥の面談室で休ませてもらったことがあるのですが、その時奧さんが毛布を持って来てくれて、ずっと気遣って下さり、メンタルが落ち込んでいたのもあって、気持ちがとても救われたのを覚えています。普段自習空間で勉強に疲れてしまったとき、いつも奥さんの声で元気になれました。ありがとうございました。
○花田先生
私にとって、塾の中で一番話しやすい先生でした。英語はずっと花田先生に担当していただいていましたが、先生の授業は、そこで出てきた英語に関する話や雑学が多く、毎回とても楽しかったです。高3のときの授業は、私の学力がクラスに追いついていなくて、ついていくのにとにかく必死でした。しかし最後までなんとか食らいついたおかげで、私立入試のときには英語がスラスラ解けました。
数Ⅲのクラス分けテストで、かなりひどい点数をとってしまい、それまで数Ⅲだけは自信があったことと、高3になってからいっそうメンタルが弱くなっていたことで、テストの結果に涙が止まらなくなり、その時ずっと先生に慰めてもらいました。あの時は迷惑をかけてしまって、すみませんでした。
今でも英語は苦手ですが、入試のときに英語がある程度戦えるようになったのは、先生のおかげです。ありがとうございました。
○桐村先生
化学も物理も大の苦手で、授業でもいつも自分だけ理解できずに思考停止していました。大学に入学した後も、去年1年生のときは、前期後期ともに化学の授業が全然理解できず、試験でも全く手応えが無い状態でした(それでもなんとか?再試験にならずに合格していました。)このようにずっと理科が苦手な私ですが、先生の授業は面白い雑談が挟まるので、いつも楽しかったです。
先生がいつだったかの授業中に「もう一度大学に通えるなら、ぜひ通いたい。これから大学生活を送る君達が羨ましい」と、おっしゃったのを覚えています。医学部は高校の時に想像していた以上に忙しく、大変ですが、今だけの大学生活を悔いの無いように過ごしていきます。
その他の先生方も関わった時間は短いですが、とてもお世話になりました。本当にありがとうございました!
長すぎる合格体験記になってしまい、すみません。
大学では覚えることが膨大にあるのに1単位でも落としたら留年…と、気が抜けませんが、せっかく現役で入学できたのだから、6年間ストレートで進級し、地域で活躍できる医師になります!